管理及び公開時の受付・ガイド(ご案内)を担当しております。 |
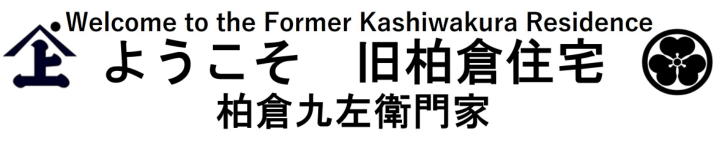
ガイド(概要) 動画はここから
国指定重要文化財の「旧柏倉九左衛門家住宅」のみどころをポイント的にご紹介いたします。
※ 柏倉九左衛門の歴史経緯は様々な言い伝えがありますが、江戸時代に、全国有数の紅花生産地として名高
かった山形の紅花は「最上紅花」と呼ばれ、その質の良さから「米の百倍、金の十倍」もの価値があるとされて
いました。
そんな「紅花の国」山形において、当時生産量最多級の豪農として名を馳せていた柏倉家の華やかで趣のあ
る屋敷をご紹介します。
 |  |  |
山形市の北西に隣接する中山町は、芋煮会発祥の地と言われています。
江戸時代には紅花生産が盛んな町でした。
その中で、村山地方でも最多量級の紅花生産をしたのが柏倉家です。
経営は地主と金融が中心でしたが、良質な紅花づくりにも励みました。
旧柏倉家住宅は、明治期の上層農家の暮らしぶりを今に伝える大規模住宅です。
当主は代々「九左衛門(くざえもん)」を名乗り、江戸時代には山形藩の大庄屋を務めていた時期もありました。
初代九左衛門が岡村に移り住んだ直後は、地主でした。 最盛期ほど大規模であったかはわかりませんが、初代九左衛門が隠居する際に九郎兵衛家を分家として出せほどはありました。 その後も土地を拡大させていき、広大な土地を所有するようになりました。
江戸時代中期には紅花の栽培を始め、次第に村山地方でも最多量級の生産量を誇っていました。 他にも稲作を栽培しました。
江戸時代後期から近代にかけて金融業にも携わり、一族の地域の有力者と共に羽前長崎銀行を経営していました。
屋敷は江戸時代後期に建てられ、明治期の大規模改修で現在の形になったといわれています。
近年、その文化的価値が高い評価を受け、2019(令和元)年に国指定重要文化財(敷地内8棟)に認定され
たほか、2018(平成30)年には日本遺産、2019(平成31)年には日本農業遺産の構成団体として多方面からそ
の魅力が認められています。