管理及び公開時の受付・ガイド(ご案内)を担当しております。 |
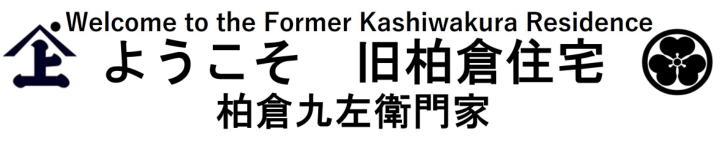
ガイド(国・重要文化財 8棟)
国・指定重要文化財の「旧柏倉九左衛門家住宅」のみどころをご紹介いたします。
旧柏倉九左衛門家住宅令和元年に国の重要文化財に指定
令和元年の国の重要文化財には、屋敷内の建物8棟が指定されました。

旧柏倉家住宅は柏倉一族の本家、柏倉九左衛門の屋敷です。
主屋、内蔵、仏間、前蔵、北蔵(米蔵) 、大工小屋、長屋門、裏門の計8棟の建物が配置されています。
この他にも、籾堂、下便所、堆肥小屋、内塀、石組の洗場や煉瓦積の穴蔵などが、良好に残っています。
今は敷地約2,300坪(約7.590㎡)で建物も約360坪(約1,200㎡)が黒板塀で囲まれています。
【主屋(おもや)/(母屋(おもや))】
 |  |
江戸時代天明3年(1738年)約300年ほど前に現在の建物配置の原型ができあがりました。
その後、明治31年(1878年)に大規模な改築によってほぼ建替えられ現在の姿になったと考えられます。
雄大な規模の茅葺民家で、山形県南部の近世農家の平面を継承し、座敷部の拡張や、吟味された銘木を多用した造りになっています。
但し、その後も小規模な改修を行っております。
南北棟木造平屋建てで茅葺寄棟造りであり、東を正面としています。
規模は桁行30.2m(16間半)、梁行9.7m(5間半)、主要面積は292.4m2(約88.61坪)。 南側桁行17.3m(9間半)を床上として諸室を設け、北側12.726m(7間)をダイドコロとして利用していました。
西側には内蔵が建ち、内蔵に至るロウカと呼ばれた板間の空間がカッテから接続し、ロウカ(老家/楼下)・コザシキといった和室が設けられ、隠居のための空間でした。
生活拠点の建物であるため、当地に移住した当初から存在していたはずだが当初の詳細は未だ不明です。
家族や使用人達の生活が営まれていました。
建物でありながら、座敷をはじめ来客の対応などを目的とした部屋が多く設けられています。
シモザシキやチャノマの他に、土間部分東面の戸口を常用し、用向きに応じて北面や西口の戸口を使用しました。
【内蔵(うちぐら)】

内蔵の内部は傷みが激しいため一般公開をしておりませんが、家の人達の居室やプライベートな置物がある内蔵で生活を営んでいました。
桁行11.1m、梁間6.5mの土蔵造り。
現在の内蔵は文献により明治4年に土蔵造りで建てられました。
前身の建物は文政年間(1818年から1831年)の頃に存在して記録があり、明治3年に解体されました。
昭和11~12年にかけてロウカの増築などが計画され、現在の位置になりました。
二階建ての銅板葺きで古くは茅葺でしたが、明治33年に栗木羽葺、大正14年に鉄板葺、平成3年に銅板葺になりました。
内部は上座敷と下座敷の二室を設け、どちらも家族の居室であり、次代の当主夫妻が主に使っていました。
二階は板敷で、文書やタンスといった家財道具など家族が使うものを収納していました。
【北蔵(きたぐら)】

北蔵は東西棟切妻造りの土蔵造りで置屋根式の亜鉛板葺(古くは茅葺)と考えられ、大正12年に亜鉛板葺となりました)の建物で、文献により明治7年の建築と判明しております。
内部は一室で元は東側に二階があり、大正14年に西側に二階が設けられたが、後に撤去されました。
昭和期に倉庫として貸し出された際に天井が外され、床がコンクリート土間に改められました。
その後平成10年代に美術館として活用する際に床が合板張に改められ、再び東側に二階が設けられました。
江戸時代には近隣から集められた年貢米が納められ、北蔵で保管されていたことから米蔵とも呼ばれました。
昭和初期に、小作米が約4,500俵とも、でも戦後期には既に納められておらず旧所有者も蔵の中に年貢米があった様子は覚えておりません。
その後は雑多な荷物や道具が置かれていました。
【大工(だいく)小屋(ごや)】

大工小屋は南北棟の木造平屋建てで鉄板葺(古くは茅葺(かやぶき)で昭和3年に鉄板葺になりました)切妻造り。 規模は桁行15.0m、梁間8.5m。
文献により天保13(1842)年に稲小屋として建てられ、明治32(1899)年に板間で大工作業場が造られたと記されています。
柏倉家には建物の管理などを行うトウリョウが常駐していました。
九左衛門家・惣右衛門家を兼務(けんむ)していたこともあります。
普段は修繕や作り物を行っていました。
屋根の葺き替えの時など人手がいる時にはトウリョウが近隣の大工や職人を集めて作業の差配をしていました。
仕事がない時には近隣で仕事することがあり、そんな時も朝に直接現場に行かず、九左衛門家で「今日はどこどこに仕事に行きます」と家族に断ってから仕事に行きました。
【裏門(うらもん)】

裏門は南北棟の木造二階建てで切妻造り亜鉛鉄板葺き(古くは杉皮葺と考えられ、明治38(1905)年に栗木羽葺き、大正8((1919))年にトタン葺き)の建物。 西を正面とし、東を裏側とする。
規模は桁行(ゆき)2.1m、梁間1.5m。
母屋桁に残された「文化十二乙亥五月再建之 大工喜之助」という墨書より文化12(1816)年に建てられたと判明しています。 「ミハリモン」とも呼ばれ、文献の中には「浦門」とも記載されています。
裏門には夜になると夜番がいました。
二階に上がるためのハシゴが置かれていました。
旧所有者は裏門に夜番がいた様子を覚えていません。
家の者がミシマヤマやハイデンに行く際はこの門を通っていました。
【仏蔵(ぶつくら)】

仏間は文献により明和7(1770)年頃に建てられ、現在の建物は明治42(1909)年から44(1911)年に改修されたもので、東西棟の土蔵造、規模は桁行9.5m、梁間5.5m。
切妻造り銅板葺き(古くは木羽葺で、明治42年に瓦葺、昭和2年に銅板葺となりました。)の妻入り。
東・北・西の三方に下屋を巡らし廊下として、東面に唐破風屋根の玄関を設けました。 大正2年に南面東側に南北棟のカミユドノを増築しました。
内部は座敷広間として東側から外陣、その西一間を内陣、西端の半間をゴウモンと区別し、外陣の三方とゴウモン西面に出入口を設けました。
外壁は軒まで漆喰で塗込め、外柱には銅板を巻いて防火に備えています。
外陣内壁は紙貼の真壁造で竿縁天井を張り、柱や長押とともに漆を塗る。
内陣は一段高く床を張り、境には朱漆塗の彫刻欄間を黒漆塗の枠に嵌めて飾りました。
正面に仏壇を置き、仏壇上部の天井は折上げて金箔を押しています。
【前蔵(まえくら)】

前蔵は東西棟土蔵造二階建てで鉄板葺(以前は瓦葺)の切妻造の建物で、規模は桁行14.3m、梁間5.7m。
北面に下屋を設けて廊下とし、東面北寄りに便所を設けました(大正元年の増築)。
文献により明治35~42(1902~1909)年にかけて新築で建てられたと判明としており、資材調達には明治35年から始められています。
また、明治36年に作成された二枚の板図があります。
現在の前蔵ができる以前にも仏蔵東側に南北棟の建物で「旧前蔵」がありました。
前蔵は来客用の座敷蔵で、賓客の歓待や寝室として使用したほか、冠婚葬祭などの際には控室としても利用されました。
一階は東から15畳の上座敷、10畳の下座敷があり、上座敷及び下座敷の北面と着替部屋西面に出入口を設けました。
二階は板敷の一室で来客用の道具(布団など)や家財(比較的上等なものなど)を収めていました。
外壁は軒先まで漆喰を塗込め、内部は柱を立てて内壁を造りました。
上座敷は違い棚でケヤキを使用はする他は春慶塗のヒバ材を多用しています。
【長屋門(ながやもん)】
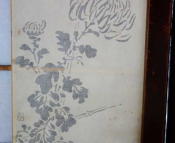 | |
 |  |
長屋門は文献により文化13(1816)年には前身の建物があった事がわかっており、現在の建物は天保14(1843)年に建てられたことが判明しております。 桁行20.7m、梁間4.7m。 切妻造、銅板葺(古くは茅葺とされた大正10年に木羽葺の上にスレート葺、昭和4年に銅板葺)、中央の門を挟んで南側をカミナガヤ、北側をシモナガヤとして、建物の南北端に便所を設けました。
門は柱間2.8mで内開きとして、北側に潜戸(くぐりど)を設けました。
昭和初期まで門は日中ずっと開け、18時頃に閉めていました。
カミナガヤは南北に二室を配し、上座敷・下座敷として使用していました。
上座敷は南面に釣床、東面北側に物入れを設け、竿縁天井を張りました。
下座敷は東面に物入れを設け、根太天井とする。
(現在、お客様用の控室兼休憩所)
シモナガヤは南から受付、事務所、物入の三室を並べる。
西面の軒は出桁造りです。
外壁は真壁漆喰塗で、東面は割竹を張って腰壁とし、側廻りの開口部に腰付障子や板戸をはめました。